はじめに - ある不思議な現象について
例えば国会で居眠りしている政治家がいます。 そんな彼らの年収は約2000万円以上だと言います。
例えばニュース番組に出て芸能人のスキャンダルを批判したり適当なコメントをするコメンテーターは、たった1 時間の仕事で約5万円近くギャラを貰っていると言います。
一方で社会に必須な仕事、介護や保育、スーパーやドラッグストア、そこに商品を運ぶトラック ドライバー、そういった「なくてはならない 仕事、人のために働く仕事」の年収はまあ良くても500万程度でしょう。
そんな事実を知った時、このように思う人がいるのではないでしょうか?
「なんかおかしくないか?」
なぜ、別になくてもいい仕事が儲かって、人のために大事な仕事をしている人が報われないんでしょう?
ご来訪頂きまして誠にありがとうございます。夕凪と申します。
この理不尽な状況について、アメリカの人類学者デビッド・グレーバーが興味深い指摘をしています。
今回は彼の考察を紐解きながら、現代の働き方について考えてみましょう。
「3時間労働」で十分だったはずの未来

実は1930年、当時を代表する経済学者のケインズはこんな予測をしていました。
「20世紀末までに、イギリスやアメリカのような先進国では、テクノロジーの進歩により、人類に必要な労働時間は週15時間(1日3時間)程度になるだろう」
さて、どうでしょう?
21世紀になった今、私たちは相変わらず週40時間働き、過労死ラインすれすれの残業まで当たり前のようにしています。
ケインズの予測は間違っていたのでしょうか?
グレーバーは「いいえ」と答えます。
「テクノロジーの観点から見れば、1日3時間労働は十分に達成可能だった。でも、テクノロジーは労働を減らすことには使われなかった。むしろ、私たちを一層働かせるために活用されてきたのだ」
ある工場の話 - テクノロジーの本来の使い方

この点について、グレーバーは興味深い例え話をしています。
ある和菓子工場では、従業員が手作業で1日8時間かけて1000個の商品を作っていました。1個200円で売って1日の売上は20万円。その売上から社員に給料を支払っています。
ある日、新しい機械が導入されました。なんと4時間で1000個作れるようになったのです!社員のみんなは「これで仕事が楽になる!」と大喜び。
...でも、会社はどうしたと思いますか?
はい!労働時間は一切減らさず、4時間で1000個作れるなら、1日の生産量を2000個に増やしたのです。そして半額の100円で売り出すことに。
1日の売上は20万円のまま。テクノロジーが進歩したのに、労働時間も売上も変わっていません。
確かに、私たちは商品を安く手に入れられるようになりました。でも、安く手に入るということは、それだけありがたみも減ります。
結局、私たちの幸福感は大して変わっていないのです。
「暇は悪」という呪い

ではなぜ、会社は労働時間を短くしようとしないのでしょうか?
グレーバーはこう指摘します。
「そもそも人の働き方とは、基本的に暇に過ごし、必要な時だけ集中するものだった。でも、いつの間にか
『暇は問題であり、罪である』
と考えられるようになったのだ。」
実は、縄文時代の人々の労働時間は1日2〜4時間程度だったと言われています。彼らには「労働」という概念自体がなく、基本的に毎日のんびり過ごし、集中する時間はごく一部でした。
それが、いつの間にか「暇は悪」という価値観ができあがり、暇な時間ができれば無理やりにでも仕事を作るようになったというわけです。
「やってる感」の蔓延

グレーバーによれば、「暇は悪」という価値観が生んだものは、実は勤勉さではありません。
「暇さを隠すこと」なのです。身に覚えがある人も多いのではないでしょうか?
たとえば...
太郎さんは仕事が早く終わって手持ち無沙汰になりました。でも「終わった」と言えば?そうですね、たいてい別の仕事を振られるだけです。だったら、終わったなんて言わない方が得策。結局、効率よく終わらせるより、だらだらと時間をかけた方が賢明という本末転倒な状況が生まれます。
あるいは...
花子さんは定時になって仕事も終わったのに、誰も帰ろうとしない同僚たちを見て「一番に帰ったらサボり魔と思われるかも...」と心配になり、仕事をしているフリを続けます。
なぜこんなことが起こるのでしょう?
グレーバーはこう説明します。
「現代の労働者は、仕事を売っているんじゃない。時間を売っているんだ。だから時間を暇に過ごすことは『窃盗』と同じになってしまっている」
しかも彼によれば、「他人の時間を所有できる」という発想自体が奇妙なものだと言います。
なぜなら、それは労働ではなく、他人の自由を奪い取る奴隷制や、刑務所への監禁と本質的には変わらないからです。
「ブルシット・ジョブ」の正体
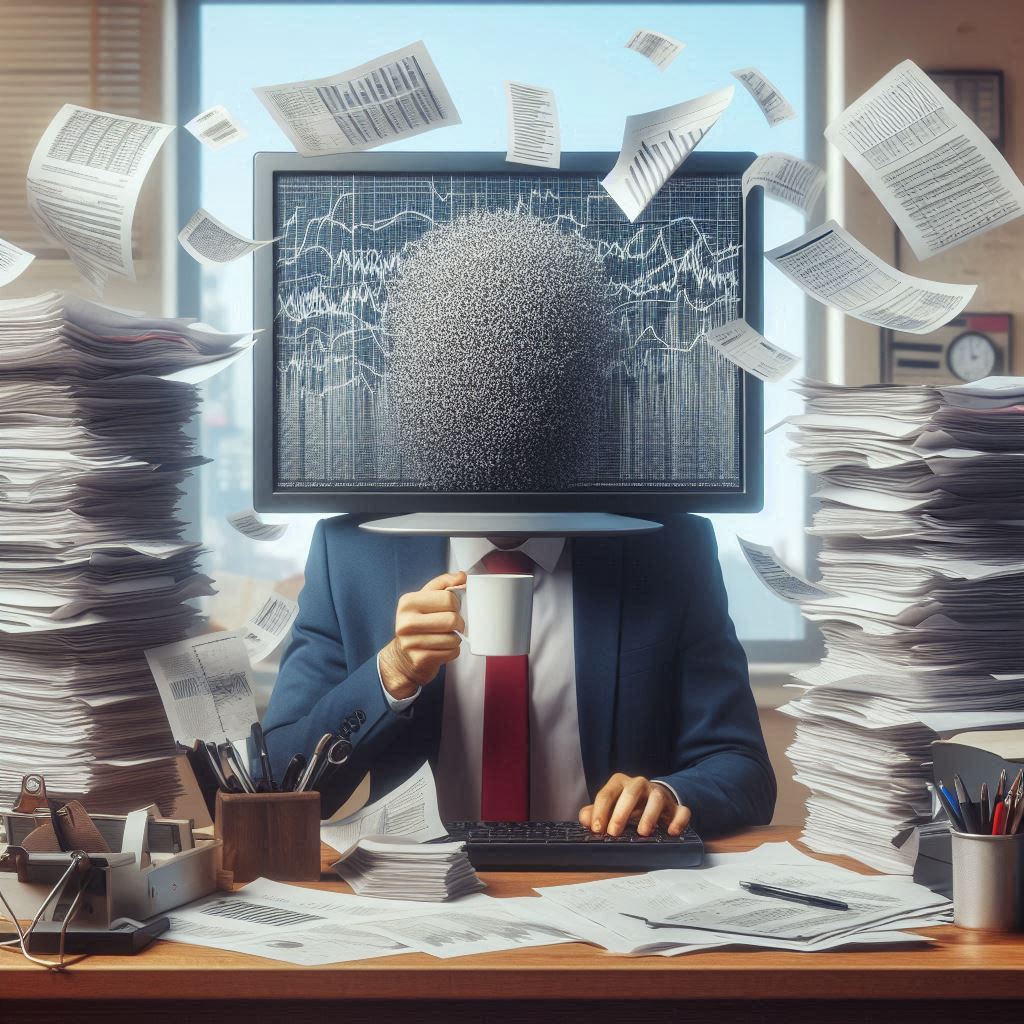
そんな「時間を埋めるための仕事」を、グレーバーは「ブルシット・ジョブ」と名付けました。
彼が友人の法律顧問と話した時のエピソードが印象的です。その友人はこう告白したのです。
「俺の仕事は全く意味のないものだ。世の中に何にも貢献していないし、なんなら存在しない方がマシかもしれない」
この話をウェブ雑誌に投稿したところ、驚くべき反響があった。
2週間で100万アクセスを超え、コメント欄は「まさに私の仕事もそう!」という告白で溢れかえったのです。
あるIT企業の社員は言います。 「私の仕事は、依頼されたら書類を作り、上司に報告して署名をもらい、下請けにメールを数通送信するだけ。それだけで給料をもらっていて、自分が依頼したものの現物を見たことすらない」
ある公務員はこう打ち明けます。 「デスクに座ってもほとんどやることがなく、仕事と関係ない哲学の研究に励んでいた。いっそのこと仕事を欠勤するようになっても何の問題もなく仕事は回っていた」
5つの「ブルシット・ジョブ」

グレーバーは、これらの無意味な仕事を5つのカテゴリーに分類しました。
1. 取巻き
誰かに偉そうな気分を味わわせるための仕事です。分かりやすい例がエレベーターガール。
別に自分でボタンを押せるのに、いい気分を味わうためだけに代わりにボタンを押してもらう。
高級ブランド品の制作や販売も、作っている人自身が「ユニクロで十分」と思っているなら、これに該当するかもしれません。
2. 脅し屋
雇用主のために相手を攻撃する仕事です。テレビのコメンテーターなんかもこれに当たるでしょう。
視聴者個人個人が感想を持てばいいだけなのに、わざわざ誰かにコメントを言わせて、スポンサーの求めるイメージに誘導します。
広告業界の人の告白が興味深いですね。
「我々は視聴者が番組を見ている間に自身に何かしらの欠陥があるように思わせ、CMでその解決策となる商品を提示して見せるのです。」
「商品を売るには何よりもまず人を欺きその商品を必要としていると錯覚させなければならない。」
3. タスクマスター
ただ部下に仕事を割り振り、監督をしているだけの管理職です。
もちろん、こういった仕事が必要な場合もありますが、上司不在でも仕事が完璧に回るのであれば「ブルシット」とみなされます。
4. 書類穴埋め
誰も読むことのない書類を作る仕事です。
5. 尻ぬぐい
他の無意味な仕事の後始末をする仕事です。
これら5つの「ブルシット・ジョブ」は特定の業種に限ったことではなく 普段の仕事の中でも山のようにあるのではないでしょうか?
ただ上司が決めるのを黙って待っているだけの会議や誰もまともに読むことがない書類を作る作業、
つまりグレーバーは「そういった仕事をなくし必要なものだけに注力すれば本来1日3時間労働で十分事足りる」と言っているのです。
それなのに「暇は悪」という奇妙な価値観のせいで空いた時間になんとか仕事を詰め込む。
そのせいで無意味な仕事が増えるようになり、のんびりした時間を失う事態に陥っているのです。
「シット・ジョブ」という皮肉

一方で、グレーバーは社会に本当に必要な仕事を「シット・ジョブ」と呼びました。
介護士、看護師、ゴミ収集、トラックドライバー、教師...。これらの仕事は間違いなく社会に必要不可欠です。にもかかわらず、社会的地位は低く、労働条件も悪く、報酬も少ない。
「くだらないことに、ブルシット・ジョブほど地位が高くなり、『価値ある仕事』だと思われて、しかも報酬も高くなりがちだ。一方、シット・ジョブは見下され、報酬も低くなっている。これほど捻じれたことがあるだろうか」
なぜこんな歪みが生まれるのでしょう?グレーバーは痛烈に指摘します。
「社会に必須な仕事ほど『社会的に意義がある』『やりがいがある』...そういったクソみたいな理屈で、賃金の低さを正当化されているんだよ」
たとえば教師が「もっと給料が欲しい」と言えば「お前は子供のためじゃなく、金のために働いているのか」と非難されかねません。
もしも教師が高級車なんて乗っていたら、子供に悪影響だ何て言われるのは目に見えています。実際現実には公務員がコンビニで休憩しているだけで文句を言う人がいます。
解決策としてのベーシックインカム

では、この歪んだ状況をどう正せばいいのでしょうか?
グレーバーは「ベーシックインカム」を提案します。
これは、政府が年齢や性別、所得に関わらず、全ての国民に一定の金額を支給する制度です。
「控えめなベーシックインカムのプログラムでさえ、最も根本的な変革に向かう最初の一歩となりうる。すなわち、労働を生活から完全に引き剥がすことである」
なぜベーシックインカムが解決策になるのか?それは…
- 労働者が無駄な仕事を生活の不安から続ける必要がなくなる。
- 企業も人を遊ばせておく必要がなくなり、無駄な仕事を作り出さなくて済む。
- 社会に必要な仕事(介護など)に人が集まらなくなれば、必然的に報酬を上げざるを得なくなる。
「ベーシックインカムを導入したら、誰も働かなくなるんじゃない?」
そんな心配をする人もいるでしょう。でも、実はそんなことはないと思います。なぜなら、人は退屈に耐えられない生き物だからです。
グレーバーはこう考えています。生活の心配をする必要がなくなり、ある程度の余裕ができてはじめて、人は自分の生き方に真剣に向き合えるようになる。そうして人々が「目覚める」ことで、歪んだ社会を正すことができる。
確かに「清いベーシックインカム」なら良い社会になっていきそうですね。生活のための労働から開放されれば本来やりたかった道へ進む人も多くなるし、エンタメやその他の文化なども盛り上がって楽しい世の中になりそうです。
しかし現在の政府および支配権力が施すベーシックインカムだとしたら、そもそも労働開放レベルの金額を支給するとは思えないし、受給するのにも端的に言えば、事実上の奴隷隷属的な条件を課してくると思われ、更に奴隷制度色が濃くなる社会になりそうですね。
1日3時間労働が効率的というデータは実際にあるのか?

ところで、1930年の経済学者のケインズの予測から、20世紀末にはテクノロジーの進化により1日3時間労働で十分となるはずでしたが、とはいえ「8時間より3時間労働の方が結果を出せる」ということが本当にあるのでしょうか?
1. 認知的・創造的な作業の最適時間
研究によると、人間の集中力が高く維持できる時間は 1日3〜5時間程度 であるとされています。
- ケンブリッジ大学の経済学者Camererらの研究では、クリエイティブな仕事(ライティング、研究、プログラミングなど)は3〜4時間が最も効率的 と示唆されています。
- 「ディープ・ワーク(深い集中力が必要な作業)」の提唱者であるカル・ニューポートも、1日4時間を超えると集中力が低下し、作業効率が大きく落ちると述べています。
2. 歴史上の偉人たちの労働習慣
過去の著名な作家・科学者・芸術家の多くは、1日3〜5時間の労働時間を採用していました。
- チャールズ・ダーウィン:午前中3時間の執筆、午後はリラックス
- ウィンストン・チャーチル:朝の数時間集中し、午後は昼寝と趣味
- トーマス・ジェファーソン:数時間の執務の後、読書や散歩
彼らは短時間の労働をすることで、高い生産性を維持していたとされています。
3. 労働時間と生産性の関係(実証研究)
労働時間が長くなると、生産性が大きく低下することが統計的にも証明されています。
- スタンフォード大学の研究(John Pencavel, 2014)
- 週50時間を超えると、労働者の生産性は急激に低下
- 週70時間労働しても50時間労働の人と同程度の成果しか出せない
- スウェーデンの6時間労働実験(2015年)
- 8時間労働のグループと比較して、6時間労働のグループの生産性が向上し幸福度も増した。
これらのデータを考慮すると、 3時間の超集中作業+適切な休息 が最も効率的である可能性は高いです。
結論:1日3時間労働は科学的に理にかなっている
完全に全ての職種で適用できるわけではないですが、特に知的労働や創造的な仕事では、1日3時間の集中作業が最も生産的 であることを示す研究は数多くあります。
「長く働く=成果が出る」という考え方は時代遅れになりつつあり、今後は短時間・高効率の働き方が主流になる 可能性が高いですね。
元来から持つ人間の集中力の限界や、実際に結果を出している歴史上の偉人の観点からも、テクノロジーの進化云々抜きで考えても労働時間は短いに越したことはなさそうです。
最後に

大昔から短時間労働の有効性だったりベーシックインカムだったり、社会を良くするための叡智は提示されていた。
だけど2000年代になった今でも、特に日本においてそれらが全くと言っていいほど反映されてこなかったのは、やはり権力支配による意図的なものを感じざる得ないのです。(あくまで個人的意見)
そして我々も見事に長時間労働=経済成長 という古いパラダイムや、働かざる者食うべからず「勤勉は美徳」という価値観などにどっぷりハマってしまい、「働いていないと自分の価値が下がるのでは?」「仕事こそが人生」「労働から解放されることに対する心理的な抵抗」などを無意識レベルで植え付けられてしまっているのかもしれません。
実際にベーシックインカムを導入したフィンランドの実験でも、一部の人は「時間がありすぎて逆に不安になった」という結果もあるそうです。
近年変化してきているとはいっても、まだまだこれらの価値観が大衆意識である以上「私は3時間で退勤致します。」ということにはいかないわけで「短時間の労働で十分富む」人生を送りたいなら、そういう社会が来るのを待つのではなく自ら動いていくしかないのでしょう。
しかしながら、いよいよAIやテクノロジーの発展により、今後は「労働時間を減らしても経済を回せる時代」が来る可能性があります。
それに伴い「短時間で効率よく働く」ことが当たり前になるような社会へとゆっくりシフトしていくかもしれません。
この変化を先取りして、自分で収益を生み出せるスキルを持つことが、これからの時代を心地よく生きるカギになりそうですね!
ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
